2025.03.31 京都府内のイベント・観光・体験
日本美術の名品を交流の軸で捉え直す/京都国立博物館「大阪・関西万博開催記念 特別展 日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」

京都国立博物館では、万博開催を記念して「交流」をテーマにした特別展を開催。古今東西の文化が混ざり合って生まれた至極の名品が一挙集結します。企画について、学芸部 列品管理室長の永島明子さんにお話を伺いました。
交流をテーマに、日本美術とは何かを考える
―― 京都国立博物館について教えてください。
京都国立博物館は明治30年(1897)に開館しました。東京の国立博物館に比べて、お寺や神社、個人の方からお預かりしている寄託品が多いのが特徴です。これには、当館の設立理由が関わっています。
当時は、廃仏毀釈運動によって全国各地で仏教関係の貴重な文化財が失われつつある状況でした。歴史が失われてしまうことに危機感を抱いた人たちによって、古社寺の宝物を守るための古社寺保存法が制定され、当館が設立されました。寺宝を安全なところで保管して、失われることのないよう国が守っているということです。
―― 博物館の設立は万博とも関係があるそうですね。
そうですね。ヨーロッパでの万博ブームを受けて、明治4年(1871)に日本で初めての博覧会となる京都博覧会が開催されました。その4年後に、京都府が京都博物館の建設を発表しています。
この京都博物館計画は中断されてしまうのですが、当時京都府が所蔵していた品は当館に寄贈されることになりました。京都博覧会からさまざまな模索を経て、現在の京都国立博物館が設立されることになったと言えます。
 明治古都館(旧 帝国京都博物館 本館) ※現在、展示は行っておりません。
明治古都館(旧 帝国京都博物館 本館) ※現在、展示は行っておりません。
―― 今回の特別展について教えてください。
万博を記念して「交流」をテーマにした展覧会を開催します。
当館での展示は通常、分野ごとに分かれていますが、今回は交流の大きな波が見えるような展示にする予定です。
また万博という機会ですので、改めて日本美術とは何か、ということに立ち返ることができるような企画にしたいと思っています。日本美術史という研究分野がありますが、実は、明治時代に日本が初めて万博に参加した頃に出てきた考え方なんです。
ですので、今回の展覧会ではまず、19世紀後半の万博が始まった頃を振り返るところから始まります。そこで当時の日本、そして日本の美術がどのような動きをしていたのかを見ていきます。
―― 当時の万博で、日本はどのようなものを出品していたのでしょうか。
最初に日本の展示が行われた時は、日本人が出品したわけではなく、来日していたイギリス人が日本で集めたものを紹介していただけで、陶磁器や漆器などの工芸品とともに笠や蓑といった民具を飾っていました。
当時の万博は自国の文化のPR合戦の場。国威を示すような素晴らしい美術品の数々が並ぶ中で、日本コーナーには農具などの民具や日用品が並んでいたんですね。しかも、植民地が集められたコーナーに。その様子を遣欧使節として派遣されていた日本人が目の当たりにして、これはまずいと、危機感を持って帰国しました。
そうして明治政府が本格的に参加したのは、1873年のウィーン万博です。その頃には日本に「美術」の概念も輸入されました。その後の数回の万博参加を経た明治政府は、1900年のパリ万博で、本格的に日本の美術を展示しようと考えます。
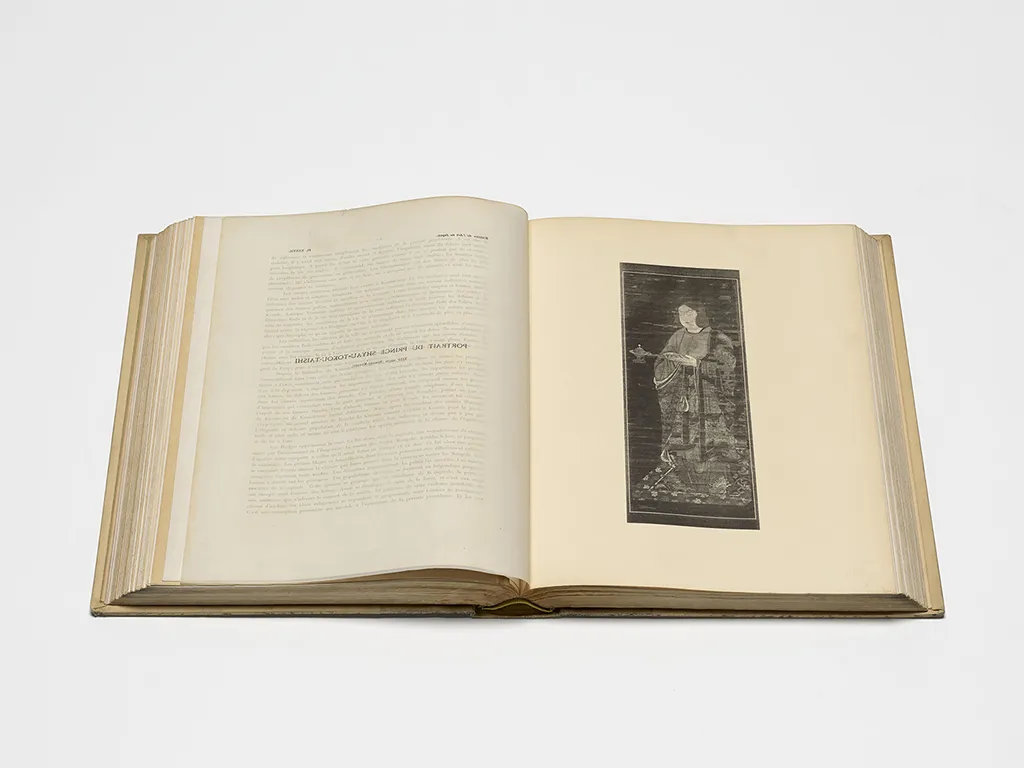 《Histoire de l'Art du Japon》(日本美術史)千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会事務局編 明治33年(1900) 京都国立博物館所蔵 [通期展示 ※頁替あり]
《Histoire de l'Art du Japon》(日本美術史)千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会事務局編 明治33年(1900) 京都国立博物館所蔵 [通期展示 ※頁替あり]
本格的に展示するにしても、日本の美術の歴史を西洋人と同じスタイルで書いて示さないと、植民地側の扱いになってしまう。そんな危機感から、明治政府は『Histoire de l'Art du Japon』という日本美術史の本をフランス語で制作します。現在国宝や重要文化財に指定されているようなものがたくさん掲載されていて、それまでお寺の奥深くに隠されていた秘仏なども、初めて広く世間に知られました。
今回の展示では本書を展示し、掲載作品の実物も一緒にご覧いただけます。
交流から生まれた日本美術の名品を、弥生時代から辿る
―― 今では当たり前の考え方も、西洋との交流から生まれていたのですね。
そうですね。概念もそうですが、日本の美術品を見ると、異国の文化の影響が色濃く映し出されていたり、交流の奇跡が見て取れたりするようなものがたくさんあります。
それを、弥生時代から見ていきましょう、というのが今回の展覧会の主眼です。大昔から東アジアの中で交流はありましたし、西洋人がやってきてからは世界規模の交流の中でいろいろなものが作られ楽しまれてきました。そうした豊かな交流を見ていただければと思います。
―― おすすめの作品はありますか。
私は漆工芸が専門なので漆推しなのですが、一番は「宝相華迦陵頻伽蒔絵そく冊子箱(ほうそうげかりょうびんがまきえそくさっしばこ)」ですね。
 国宝 宝相華迦陵頻伽蒔絵そく冊子箱 平安時代 延喜19年(919) 京都・仁和寺所蔵 [通期展示]
国宝 宝相華迦陵頻伽蒔絵そく冊子箱 平安時代 延喜19年(919) 京都・仁和寺所蔵 [通期展示]
空海が唐から持ち帰ったお経を入れるために作られた箱で、唐風のデザインです。金銀で飾られていて、古風な唐草が円を描くように配置されているのですが、よく見ると、28の迦陵頻伽が描かれています。
迦陵頻伽というのは、上半身が人、下半身が鳥で、とても綺麗な声をもつ生き物です。仏教では、極楽浄土で仏法をさえずっている霊鳥とされています。ここに描かれている迦陵頻伽は、楽器を奏でたり、踊ったりとそれぞれが違う姿をしていて、とても可愛いんです。唐風のデザインなのに、顔が少し日本風なのもポイントですね。
 作品の拡大図
作品の拡大図
これほど柔らかに漆で描くには、非常に高度な技術が必要です。また、平安時代のもので、作られた年号や経緯までわかっているものは大変珍しいんです。今回は箱だけの展示ですが、中身の経典もきちんと残っています。箱は、1900年のパリ万博でも展示されたんですよ。
―― 中国と日本の交流によって生まれた名品ですね。
実は、もっと大きな交流も見えてきます。
ギリシャ神話にセイレーンという海の怪物がいますよね。上半身が女性で下半身が鳥、そしてやっぱり美しい歌声をもっていて、船人を惑わすといわれています。
半分人間、半分鳥の生き物が、東では浄土の鳥になり、西では船乗りを惑わしている。こうした大きな流れで「交流」を捉えるのも、面白いのかなと思います。
―― 展示の中で工夫している点はありますか。
ずっと時代順にみていくのも疲れてしまいますから、途中にコラム企画「誤解 改造 MOTTAINAI(もったいない)」を用意しています。
舶来品がやってくると日本でもそれを真似たものを作ろうとするのですが、異国の文化ですので、うまく理解できない部分もあるんです。
例えば中国の鏡を模しましょうとなった時に、その鏡には馬車が描かれているのですが、当時日本には馬車がなかったので、カタツムリのようなものを描いてしまうんです。四つ足ではあるんだけれども、馬ではない何かファンシーな動物が描かれていて。
他の部分は本当に上手に真似しているんです。決して技術が無かったわけではありません。そのカタツムリらしき絵も、完成度は高いんです。この、ちょっとした誤解から生まれる面白さも楽しんでいただけたらと思います。
自分にとって、その作品をどう感じるか
―― 鑑賞のポイントを教えてください
目の前にある作品を自由に見て、楽しんでいただきたいです。
エピローグでは、ボストン美術館の「吉備大臣入唐絵巻(きびだいじんにっとうえまき)」を展示します。絵が漫画のようで、それだけでも十分楽しめる作品ですが、この作品には、当時ハーバード大学で日本美術を教えていた美術史家の矢代幸雄氏が語った、あるエピソードがあります。
この絵がボストン美術館に渡ったのは、日本が戦争に突き進んでいく時代でした。ですから、アメリカにおける日本のイメージは良いものではありませんでした。
そうした中で絵巻物がボストン美術館でお披露目されることになったので、矢代氏は絵巻物が散々に言われてしまうのではないかと心配していたそうです。しかし実際には、大勢のボストン市民が絵を楽しんでいました。他国の文化であっても、たとえそれが敵国のものであっても、そういうことは関係なく、美しいものは美しい、面白いものは面白いと思える瞬間が確かにあり、その力に感激したと矢代氏は後に回想しています。
 京都国立博物館 学芸部 列品管理室長 永島明子さん
京都国立博物館 学芸部 列品管理室長 永島明子さん
自分にとって目の前にある作品をどう感じるのか。こう見てほしい、と言われた見方ではなく、自分の見方で楽しんでもらいたいです。注目するポイントを変えれば、同じ作品でも違った魅力が見えてきますので、自由に見てもらえたらなと思います。
―― 最後に、万博に向けての意気込みをお聞かせください。
多くの人に楽しんでもらえる展示にできるよう、海外の方が日本の文化に触れられるようなワークショップも企画していますし、音声ガイドやテレビ番組の放映の準備も進めています。
ただ、一つお伝えしたいのが、大阪や奈良で国宝展が開かれますが、当館は国宝展ではないということです。
本展でも国宝の展示はありますし、国宝は素晴らしいものであることには違いないです。ですが、ただ「すごい!」で終わってしまってはもったいない。
作品の一つひとつが、先人が一生懸命伝えてきたもの。ひとつひとつの品が伝える物語に耳を澄ます機会になればと思っています。
 平成知新館 外観
平成知新館 外観
企画展・美術館情報
- 展覧会名
- 大阪・関西万博開催記念 特別展 日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―
- 会期
-
2025年4月19日(土)~6月15日(日)
前期展示:4月19日(土)~5月18日(日)
後期展示:5月20日(火)~6月15日(日) - 休館日
- 月曜日(ただし、5月5日(月・祝)は開館、5月7日(水)休館)
- 開館時間
-
午前9時~午後5時30分(入館は午後5時まで)
金曜日のみ午前9時~午後8時(入館は午後7時30分まで) - 所在地
-
京都国立博物館
京都市東山区茶屋町527 - ホームページ
- https://www.kyohaku.go.jp/

